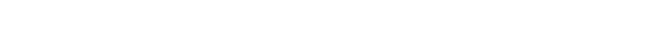
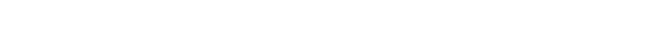

国指定重要文化財指定「石場家」の台所の囲炉裏(弘前市)
縄文時代の竪穴式住居跡にも見られるように、「囲炉裏(いろり)」は古くから私たちの生活に深い関わりをもっていた。家族が集まって暖をとったり煮炊きをしたり、夜なべ仕事のかたわらでは子どもたちがお年寄りから昔話を聞いたりと、囲炉裏は温かな交流の場でもあった。
津軽地方では囲炉裏を「シブド」「シボド」等と呼び、昭和の初め~中頃まではどこの家庭でも見られた。囲炉裏を囲む時は、奥を背にして主人の座る「横座」(ヨコジャ)、横座から見て台所に近い席は主婦が座る「嬶座」(カカザ)、その向かいは来客席の「客座・男座」、横座の向かいは「キシモト」で嫁や次男・三男・雇い人が座る場所と、立場によって席が決まっており、家族内の序列秩序を再確認する機能も備えていたようだ。

昭和31年(1956)頃の囲炉裏の風景。(青森県立郷土館:提供、佐々木直亮氏撮影)

昭和31年(1956)頃の囲炉裏の風景。ストーブに変わっていった。(青森県立郷土館:提供、佐々木直亮氏撮影)


上/常居(じょい=居間)の囲炉裏。畳を敷くのを禁じられていたため、板敷きのまま。下/台所の囲炉裏。
※ともに大農家「旧平山家住宅」(五所川原市)
江戸時代、燃料として最も多く使われたのは薪と木炭である。西目屋村砂子瀬地区では、夏に切り倒した木を冬にそりで岩木川の川岸まで運んでおき、春の雪どけ水を利用して川に木を流す「ハルキナガシ」をした。弘前の樋の口には土場が設けられ、ここまで流れ着くのに半月かかった。昭和初期の頃、村から弘前まで運んだ薪は7200タナ(1タナは薪を約縦180㎝、横180㎝に積み上げた量積)。これが街の人々の一年間の燃料になった。
炭には「白炭」と「黒炭」があるが、津軽では白炭の製炭が主流だった。砂子瀬地区では近年まで炭焼きが行われ、重い炭俵を背負って12㎞の山道を下り田代地区で米に替えるのは女性の仕事である。モンペ姿の「目屋人形」は、そうした女性をモデルに作られた。

昭和のはじめ頃より地方豊かなお土産品としてあった目屋人形。
山が遠く薪が不足しがちな西津軽郡の新田地帯では、葦などが堆積した泥炭層から掘った「サルケ」を燃料に活用した。
つがる市木造地区に住む須藤菊江さん(当時76歳)は、「湿地帯を50~70㎝ほど掘って40㎝角の正方形に切り、土手で乾かした。10~20日間ほどで乾燥するので家の裏に積み上げて保管し、ひと冬使った。昭和30年代初めまでは囲炉裏や薪ストーブに重宝したが、部屋中煙で真っ黒になるので大変だった。明治40年生まれの姑は、自ら馬に乗って近隣に売り歩き、結構な副収入になったようだ」と、当時を振り返る。

炭団(たどん)/粉炭(こなずみ)にふのりを加えて練り、丸くして乾燥した燃料。

泥炭(サルケ)/湿地や浅い沼に生える水生植物やコケ類が枯死•堆積してできる。(五所川原市歴史民俗資料館:所蔵)
揺らめく炎を囲んでの家族団らん。かつての光景が甦るかもしれない。「最後まで大切に使い尽くす」という、エコが当たり前だった時代の人々の想いが息づく暖房器具がある。廃材や樹皮など、木質バイオマスと呼ばれる資源を利用した、薪ストーブやペレットストーブだ。廃棄され、或いは山にうち棄てられていた資源を活用し、森林保護や活性化に繋げようとする試みは全国各地で行われている。
江戸では武士階級や裕福な町民などを中心に、火鉢や行火(あんか)、炬燵(こたつ)などが使われた。いずれも木炭を使うため煙や煤(すす)が発生せず、また可動式であるため重宝した。隙間の多い日本家屋では、室内全体を暖めるのは非常に効率が悪く、経費もかさむため、「頭寒足熱(ずかんそくねつ)」のスポット暖房は理にかなっていたのだろう。

手持ち火鉢と飯櫃(めしびつ)を保温する「エンツコ」。(五所川原市歴史民俗資料館:所蔵)

「安全アンカ(戦前)」。どの方向に倒れても中の炭がこぼれない設計になっている。(青森県立郷土館:所蔵)

こたつと幼児を入れて遊ばせる「エンツコ」。保温の効果もある。(青森県立郷土館:提供、佐々木直亮氏撮影)
火鉢は、銅、鉄、真鍮などの金属製や木製、円形の陶製品など材料も形もさまざまで、灰に木炭を入れて使用した。長火鉢は火鉢と家具を合体したもので、鉄瓶でお湯を沸かす、お燗をつける、金網で餅を焼くという以外にも、引き出しにタバコを入れられるなど多機能で、どことなく粋な雰囲気も漂う。行火は、瓦製の火入れを焼き物や石・木製の箱の中に入れ、直接手足を当てて暖める道具。燃料は木炭や炭団(たどん)、後には豆炭が使われ、寝る時は布団に入れて足もとを暖めた。
炬燵には、囲炉裏の上に櫓(やぐら)を置き布団を掛けて使う「掘り炬燵」と、行火などに布団を掛けた「置き炬燵」があった。江戸では武家屋敷の「炬燵開き」は旧暦の10月初めの亥の日、町屋の一般庶民は次の亥の日という習わしがあった。亥は陰陽五行説では水を表すことから、火難を逃れるとされた。
湯たんぽは、もともと陶製が多かったが、昭和初め頃になると金属製も登場する。使用した湯は、翌朝には洗顔などに再利用した。
カイロは、囲炉裏などで温めた石を布に包み、懐に入れて体を暖めた「温石(おんじゃく)」が始まり。近代になると懐炉灰や白金懐炉なども発明され、最近では酸化熱を利用した使い捨てカイロが主流となった。

やぐらこたつ。中に安全アンカをぶら下げても使用した。

火鉢(せいぜい昭和くらいか?)。火鉢を使ったのは商家などの町人や武家など。

アンカ(昭和30〜40年代まで使われていた)。アンカも火鉢同様、町家などで使われた。

陶器製の湯たんぽ(江戸時代と思われる)。

カイロ(戦前)。炭を入れて使う。足下に置いて使うタイプか。(上5点とも青森県立郷土館:所蔵)
上記の参考文献・資料
『砂子瀬物語』森山泰太郎:著(津軽書房)/『青森県の百年』小岩信竹 他:著(山川出版社)/『女人津軽史』山上笙介:著(北の街社)/『日本の民俗2 青森』森山泰太郎:著(第一法規)/『みちのく民俗散歩』田中忠三郎:著(北の街社)/HP「日本の暖房の歴史」
取材協力
旧平山家住宅/青森県立郷土館/五所川原市歴史民族資料館/五所川原市教育委員会